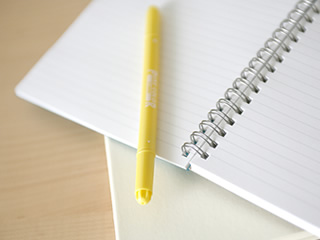|
2024/8/17
|
|
言葉の難しさ |
|
|
昨日(8月16日)より、夏期講習後半がスタートしました。 心配された台風も、さいたま市西区ではそれほどの影響はなく、予定通り開講することができました。 何より、台風で被害に遭われた方にお見舞い申し上げます。 先日閉会したパリオリンピックですが、連日のように日本人選手やチームの活躍が伝えられてきました。 (私も含めて)オリンピック視聴で、寝不足になった…という方もおられるかと思います。 連日のメダル獲得や入賞のニュースに元気づけられた人も多くいるのではないでしょうか? その一方で、多くの人が期待しているような結果が残せなかった(そもそも出るだけで凄いのですが)選手に対するSNS等での誹謗中傷が少なからずあり、日本を代表して各国の選手と競い合った選手たちを苦しめている、という残念なニュースも耳にしました。 そういったことをする人たちの中には、元々その選手やチーム、競技の熱心なファンだった人も少なからずいると思います。 むしろ、熱心なファンだからこそ、(その人が思うような)結果を残せなかったことに大きな失望や喪失感を覚えてしまうのかもしれません。 ただ、だからといって、その失望を怒りに変えて、あまつさえ言葉にして相手にぶつけてしまうことはあってはならないことです。 一昔前までは、私たち多くの一般人は、自分が生きている社会の外側に対して自らを表現する術がありませんでした。 今はそうではありません。 いつでもどこでも、だれに対してでも自らの意見、あるいは感情さえも、言葉として発信することが可能です。 言葉とは、一度発してしまったものは、話し手ではなく聞き手(受け取り手)のものだと思います。 つまり、自分がどのような意図で発したかではなく、相手がどう受け取ったか、の方が優先されると考えています。 良かれと思って言ったことが相手を傷つけてしまうこともあれば、逆に、何気なく発した一言が、相手にとって大きな助けにあることもあります。 言葉を誰もが気軽に発信できる時代になったからこそ、言葉の使い方に対するリテラシーが以前よりもはるかに求められるようになってきているのではないでしょうか。 そして、そういったリテラシーの教育や周知が、SNS等の媒体の急速な進化に対して追いついていないと痛感します。 私たちの仕事も、この「言葉」を使います。 こういったブログは、もしかしたら塾の関係者以外の「直接お会いしたことのない方」も読んでくださっているかもしれませんが、基本的には生徒や保護者の方といった身近な方を対象に、私たちは言葉を用いて勉強を教えたり相談をしたりしています。 特に生徒に関しては、大人と子ども、あるいは講師と生徒という上下関係を前提とした言葉を発していないか、その点には特に注意が必要です。 もちろん、毅然と対応すべき時には厳しいことを言う、という姿勢は大前提となります。 その姿勢がなければ、単に生徒(子ども)に媚びるだけの講師(大人)になってしまいます。 ただ、そういった厳しい言葉を相手の心に届けるためのポイントとなるのは相手との信頼関係、もっと言えば相手に対する敬意の有無ではないでしょうか。 年齢や立場に関係なく、相手を一人の人間として尊重する姿勢こそが敬意であると思います。 そして、その敬意の存在を前提として発する言葉は、たとえ相手にとってそのときは耳に痛い言葉であっても、無意味に傷つけることはないと思います。 |
|
| |