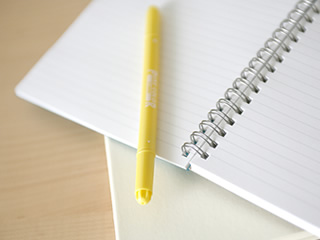|
2022/3/9
|
|
チャレンジすることとは |
|
|
昨日(3月8日)、今年度江藤塾で唯一国公立大学を受験したT君から、東京都立大学理学部数理科学科に合格した、という嬉しい報告がありました。 大学入試の結果もあらかた出そろい、あとは、後期入試を受験している生徒の発表を待つのみです。 この生徒も、既に複数の大学に合格していますが、より行きたい大学に最後までチャレンジしたいということで3月に行われる後期入試に挑戦しています。 入試において、この「チャレンジする」という言葉をよく耳にします。 一般的に、チャレンジは前向きな言葉として使われます。 ただその一方で、チャレンジをむやみに美化してしまうと、その生徒の問題点を覆い隠してしまう危険性もはらんでいるように思います。 複数の大学を受験することができる大学一般入試においては、「チャレンジ」は当たり前になっています。 多くの生徒が、 ・チャレンジ校 ・実力相応校 ・滑り止め校 の3つの基準に分けてそれぞれの受験校を決定します。 滑り止めがある前提で、チャレンジが認められやすい状況になります。 反面難しいのが、公立高校入試における「チャレンジ」です。 1回しか機会がない公立高校入試において、チャレンジがどこまで認められるのか、それはいくつかの決定要因によって大きく左右されます。 主なところでは、 ・公立高校と私立高校との学費や経費負担の違い があります。 公立高校受験に失敗した場合は、私立高校に通うことになります。 その点で、かかる費用の違いや実際に(第一志望校ではない)私立高校に通うことに対して、シミュレーションをしておく必要があります。 但しこれは、各ご家庭で判断いただくことですので、塾からの関与は原則できません。 また、当然ながら、 ・合格の可能性 も大きな決定要因となります。 こちらは、逆に、判断するうえで塾が大きく関与できる要素となります。 チャレンジしたいということは、現状では合格の可能性がそれほど高くない学校を視野に入れていることになります。 その場合は、合格基準とのギャップや課題となっている教科、そしてその対策方法も、合格の可能性とともに明確に伝えます。 これらはともに、数字やデータという客観的な指標で示すことができますので、生徒にも保護者の方にもわかりやすい判断基準となります。 ただ、生徒が「志望校を上げたい」というときに、私(塾長)が重視し、保護者の方にも確認していただきたい基準は、上記以外にもう一つあります。 中3の夏~秋にかけての面談では、保護者の方から 「成績が伸びてきたので志望校を上げたいと言っているのですが、大丈夫でしょうか?」 という相談をよくいただきます。 その際に私が必ず確認するのは、上記の指標に加えて ・保護者の方から見て、子どもがチャレンジに値する行動をとっているか という点です。 生徒からも、 「〇〇高校に志望校を変えたいけど、大丈夫ですか?」 という相談を受けます(今年度は特に多かったです)。 その場合、多くは、従来の志望校より偏差値が高い高校を希望してきます。 もちろん、どこを受けるかは個々の自由ですが、生徒の気持ちや言葉だけで 「チャレンジはいいことだよ!ぜひ頑張ってみよう!」 とはとても言えません。 (これは単に、「チャレンジ」という語感の良さに酔っているだけであり、それこそが耳ざわりの良い言葉が孕む危険性だと思います) 受験は生徒一人の力で受けられるものではなく、周囲(保護者や学校、塾)のサポートがあって可能になります。 また、高校に進学するには学費や交通費などの費用がかかります。 単純に生徒の「〇〇高校を受けたい!」という気持ちだけでは簡単に認められるものではなく、保護者の方の理解や承認があって初めて、チャレンジする権利が得られると考えています。 そして、その権利を得るには、生徒の日々の行動(学習面も生活面も)がチャレンジに値するものかどうか、その点が大切になるのではないでしょうか。 高い目標をもっているならば、それにふさわしい振る舞いが自然にできているはずです。 日ごろはあまり勉強をせずにスマホやゲーム三昧、でもチャレンジはしたい、というのはムシのいい話ですし、成功する確率も当然低くなります。 江藤塾は学習塾ですので、受験生の第一志望全員合格を大きな目標のひとつとしています。 ただ、それは決して目的ではありません。 全員合格が目的化してしまうと、特に公立高校の進路指導において、合格する可能性が高い学校のみを勧めることになりかねません。 それは、受験という人生における大切な成長の機会を、十分に生かしているとは言えないようにも思います。 肝心なのは、 ・周囲の理解を得たうえで、最終的に自分で受験校を決めること ・そしてその決定には責任が伴うことを自覚し、それにふさわしい行動をとること ではないでしょうか。 江藤塾では、チャレンジは大いに推奨しています(現に、今年も少なからずいました)。 高い目標を持つこと自体は素晴らしいことです。 ただ、チャレンジする権利は、あくまで周囲(保護者の方や塾など)から「応援される」「信頼される」ことで得られるものだと思います。 また、周囲からの応援や信頼が得られた受験生は、ほぼ間違いなくチャレンジに成功する、ということも、これまでの経験上、確かなものであると実感しています。 ・・・長くなりましたが、今年の高校・大学受験を振り返ると、「チャレンジ」がキーワードだったように思いましたので、チャレンジすることについての塾としての考えを記しました。 お読みいただき有難うございました。 |
|
| |