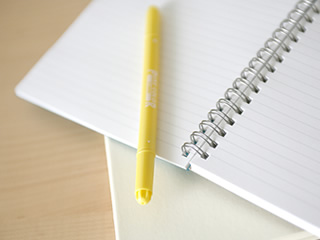|
2021/9/11
|
|
自分で言葉にしてみる |
|
|
土曜日は、中3の受験対策(理科社会)が行われます。 今年度は、理科は先日のブログでも紹介したO先生、そして社会はY先生が担当しています。 そのY先生が、「解答に至る過程を、自分で文章や図を使って説明するレポートを作る」という宿題を先週生徒に出題しました。 本日、生徒たちのレポートが提出され私も見ましたが、それぞれが自分で考えたプロセス(過程)を、熱心に書いてきてくれていました。 特に、社会が得意なMさんは、ルーズリーフにびっしりと、文のみならず日本地図やグラフを用いて非常に詳しく説明してくれていました。 Y先生は、いつも非常に熱心に説明を加えてくれます。 例えば歴史ならば、「どうしてその出来事が起きたか?」といった背景も、豊富な知識を生かして面白く話をします。 生徒は興味深く聞いてくれるのですが、塾内のテストや北辰テストを分析すると、「教えたはずの」問題ができていない・・・この事実にY先生は悔しい思いをしてきました。 そこで考えたのが上記の宿題です。 これは、Y先生の友人でもある、主に数学を担当しているS先生から教えてもらいましたが、脳科学の観点から言えば、「人から教えてもらった内容」は僅か5%しか定着しないとのこと。 これでは、いくら面白くわかりやすく説明を受けても意味がありません。 ではどうしたら定着するのか・・・ もちろん大量の演習や反復は有効です。 ただ、最も効率よく定着する方法は、「人に説明する」ことです。 学校や塾の先生がどうして教える内容を忘れないのか・・・ もちろん日々努力もしていますが(笑)、やはり「説明できる」内容は忘れないものです。 そして説明できるようになるためには、知識の整理(知識の体系化・言語化)は不可欠です。 聞いて「なんとなくわかった気になること」だけではもったいないです。 なんとなくわかったことを言葉や文章にすることで、自分の理解していない点が明確になります。 自分が理解できていることとできていないことを具体的に知ること、それは学ぶことの意義の一つではないでしょうか。 |
|
| |